腸内フローラと乳酸菌生産物質の関係
 「腸内フローラ」は常に善玉菌優勢であることが望ましい……とはいっても、加齢や現代的食事習慣のもと善玉菌優勢の腸内を維持するのは簡単なことではありません。
「腸内フローラ」は常に善玉菌優勢であることが望ましい……とはいっても、加齢や現代的食事習慣のもと善玉菌優勢の腸内を維持するのは簡単なことではありません。では、どうすれば良いのでしょうか?!
こちらでは、そのヒントとなる腸内フローラと乳酸菌生産物質との結びつきについて説明いたします。
 乳酸菌生産物質について
乳酸菌生産物質について
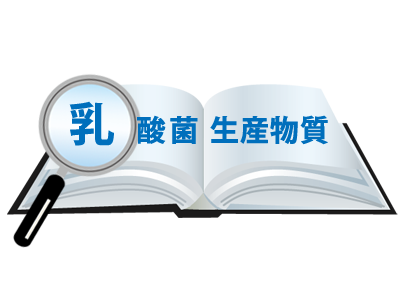 腸内フローラに住んでいる乳酸菌やビフィズス菌は、日々、ヒトの健康に寄与する成分を作りだしています。
腸内フローラに住んでいる乳酸菌やビフィズス菌は、日々、ヒトの健康に寄与する成分を作りだしています。本来は人間の営みとして体内で作られるその成分を、体の外で効率良く作りだしたモノ……これを、乳酸菌研究に生涯を投じた正垣一義は、乳酸菌生産物質と呼びました。
彼は、その産物をヒトが摂り入れる目標について、「人間の腸内細菌叢(腸内フローラ)を常に正常に維持させることであり、病気や老化により劣化した腸内フローラの修復を、この乳酸菌生産物質でいかに補佐するかが重要である」と説いています。
 腸内フローラの中の乳酸菌生産物質のはたらき
腸内フローラの中の乳酸菌生産物質のはたらき
乳酸菌生産物質は、腸内フローラを正常化するだけでなく、通常ならば腸内フローラで代謝されるものと同等の物質を摂取することにより、腸内フローラの力を借りずに人間の細胞に直接働きかけ、健康を回復維持することに役立つものと考えられています。
 腸内フローラは細菌同士が常に共棲状態にあり、ヒトの腸に付着して腸壁との共生関係も保っています。その代表的な善玉菌種がビフィズス菌や乳酸菌です。腸内において数種の善玉菌が共棲しており、その共棲グループ同士が力関係を維持して良好な腸内環境を作り出します(今風に言えば「善玉菌のシェアハウス」!?)。
腸内フローラは細菌同士が常に共棲状態にあり、ヒトの腸に付着して腸壁との共生関係も保っています。その代表的な善玉菌種がビフィズス菌や乳酸菌です。腸内において数種の善玉菌が共棲しており、その共棲グループ同士が力関係を維持して良好な腸内環境を作り出します(今風に言えば「善玉菌のシェアハウス」!?)。この運命共同体ともいえる腸内細菌の世界は、ヒトが生まれた時から死に至るまで、その場所に定住するグループなので、後から新しい菌種が参加できないのが現実です。
しかし、唯一このグループに受け入れられる「物質」が、乳酸菌生産物質です。体外で限りなく腸内に近い環境で、数種の乳酸菌グループを共棲培養させて得られた代謝産物や菌体成分です。これらは腸内フローラに良い影響を与えて、直接、腸壁からも体内に吸収されます。
 目標はヒトの腸内フローラ
目標はヒトの腸内フローラ
乳酸菌生産物質はあくまでも、腸内フローラ由来の菌によりグループ化する必要があります。これには永年の研究期間を必要とします。当社の研究にて、2種類から4種類で共棲するグループを50グループ以上所有しております。ちなみに共棲できるのは4種類以内までで、5種類以上の共棲状態はありません。経験則からの考察になりますが、おそらくヒトの腸内フローラの中で形成されているグループも、1グループずつ見れば菌種は4種類以内なのではないかと考えられます。それらのグループが多く存在して腸内フローラを形成しているのではないかと推察しますが、詳しくはまだ解明されておりません。
共棲培養のポイントとしては、あくまでも2~4種類の菌株が、いくども世代交代を繰り返してながらも同じ菌株が存在している状態を指します。単に相性の良い一種類の菌株を混合しただけではありません。その場合は共棲培養ではなく混合培養となり、ヒト腸内フローラの構成とは遠いものとなります。
共棲状態にあるチームを保持するには、長い年月の研究を要します。そしてこの技術にも限界があり、光英科学研究所では、一番安定した組み合わせの集大成として16種35株での製造に至っております。

