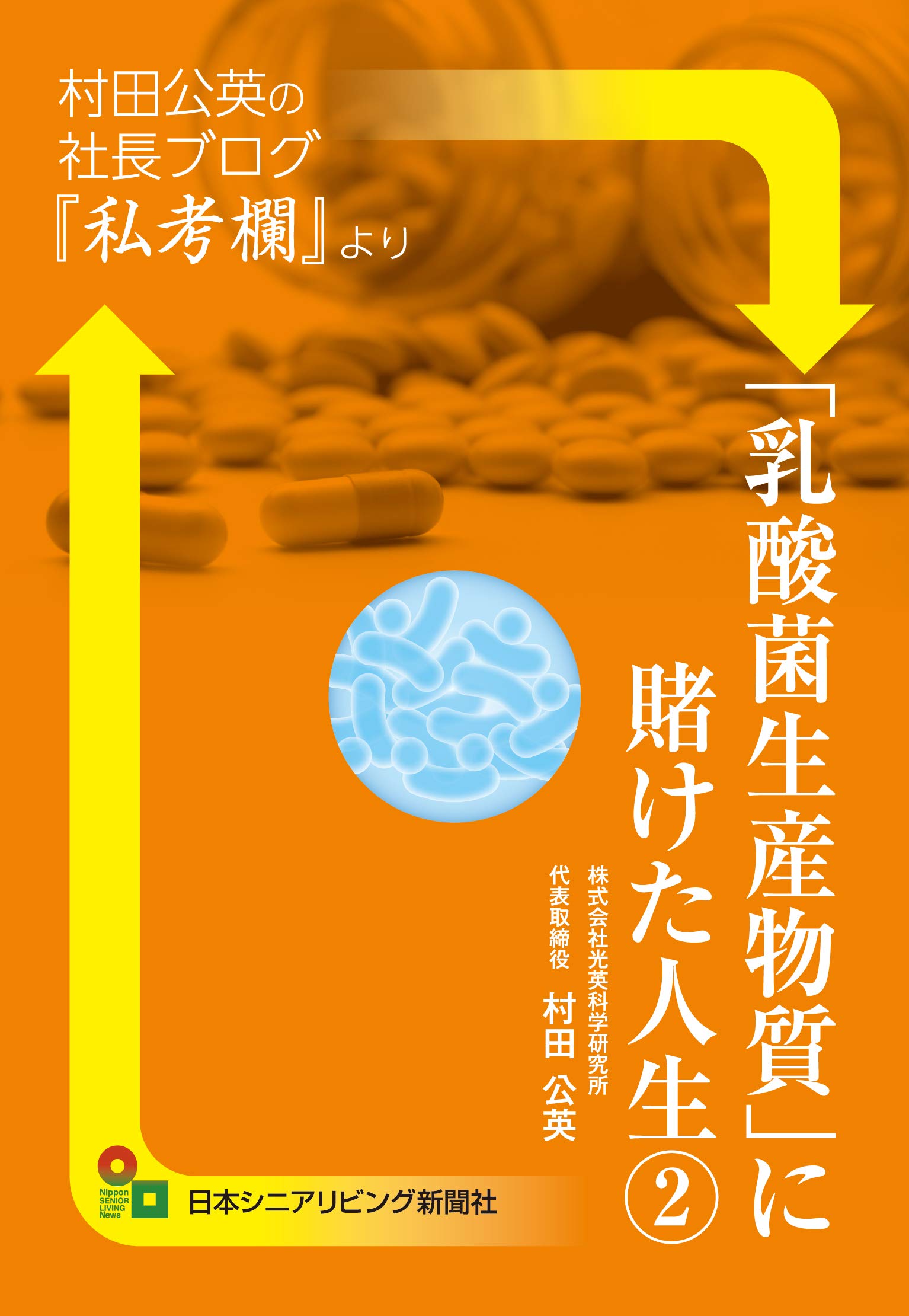2025.02.21
私的腸内細菌論
第172回 乳酸菌生産物質の製造の特徴①「16種35株の乳酸菌・ビフィズス菌」
寒中お見舞い申し上げます。
異常気象による積雪や大雪になっている地方のみなさま、どうぞ十分にお気をつけください。
さて、前回のブログでは乳酸菌生産物質のエビデンスについて、学術的な成り立ちについてお話をさせていただきましたが、今回から何回かに分けて、乳酸菌生産物質の製造についてその特徴的な事柄を中心にお話を進めて参ります。
まず大きな特徴は、乳酸菌生産物質の製造のスターターとして使用している乳酸菌・ビフィズス菌です。
これは長い年月をかけて相性の良いもの同士を組み合わせ、継代培養を行ってきたもので、(一財)日本食品分析センターで同定を行い、分類学上の学名を確認しています。
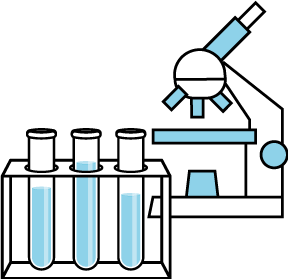 実はこの同定試験は、当社から提出した検体が多数に及んだこともあり、2003年2月から2005年4月という2年余りの長い期間がかかりました。
実はこの同定試験は、当社から提出した検体が多数に及んだこともあり、2003年2月から2005年4月という2年余りの長い期間がかかりました。
現在でこそ同定試験は遺伝子レベルで行うことが主となり、短期間で結果が出るようになっていますが、その当時は一つひとつの菌株を分離し、それぞれの性状を確かめる必要があったのです。
結果、当社の乳酸菌生産物質のスターターを構成している菌が「16種35株の乳酸菌・ビフィズス菌」であることが確定したのです。
私は長年の研究において、乳酸菌・ビフィズス菌で16のグループを形成する方法を用いて、乳酸菌生産物質のスターターを完成させました。
ですから、同定試験において16種類の菌種が判明したのは想定内だったのですが、菌株が35株に及ぶことに驚きました。
おそらく、乳酸菌・ビフィズス菌の相性の良い菌同士を組み合わせる研究過程において、菌の株のレベルにて性状の一部が変化した結果、35株という結果になったものと推察します。
その変化は、菌同士がお互いに共存するために起こった現象だと思われます。
人間においても言えることですが、他者とグループを組もうという時、いきなり相性がピッタリで上手く動き出すことはあまりありません。
時間をかけてお互いに話し合いをしたり、自分を変える工夫をしたりすることで、グループとしての成果を出すことができます。
菌も同じで、栄養物や培養の環境を変化させながら時間をかけて培養を繰り返していくことが必要です。
その結果、菌同士が工夫してお互いが必要とするようになります。
同定試験で16種35株の乳酸菌生産物質のスターターが確定し、私は乳酸菌生産物質の未来への発展が約束されたと確信するようになりました。
一つの菌だけではなく、複数の菌がグループとしてお互いが共存するからこそ得られるものが大きいのです。
私は、今では16種35株の「チームKOEI」と愛称しています。
みなさまが乳酸菌生産物質の素晴らしさを感じていただいたときは、どうぞ「チームKOEI」にエールを送ってください。

次回は製造に使用する菌の栄養物(エサ)についてお話をしてまいります。
どうぞお楽しみに。
近年は健康食品市場だけでなく、一般的にも「健康には乳酸菌」という概念が定着しつつあります。
しかし、人の健康に役立つのは乳酸菌そのものだけではなく、その代謝物である「乳酸菌生産物質」がより重要です。
この本には、16種35株のビフィズス菌を含む乳酸菌の共棲培養技術のノウハウや、「乳酸菌生産物質」の商品化の知識など、私の視点から見た「乳酸菌生産物質」に関する情報が余すところなく盛り込まれております。
ぜひ第1巻に続き、第2巻もお手元で開いていただければ幸いです。
日本シニアリビング新聞社はこちらから
amazonはこちらから