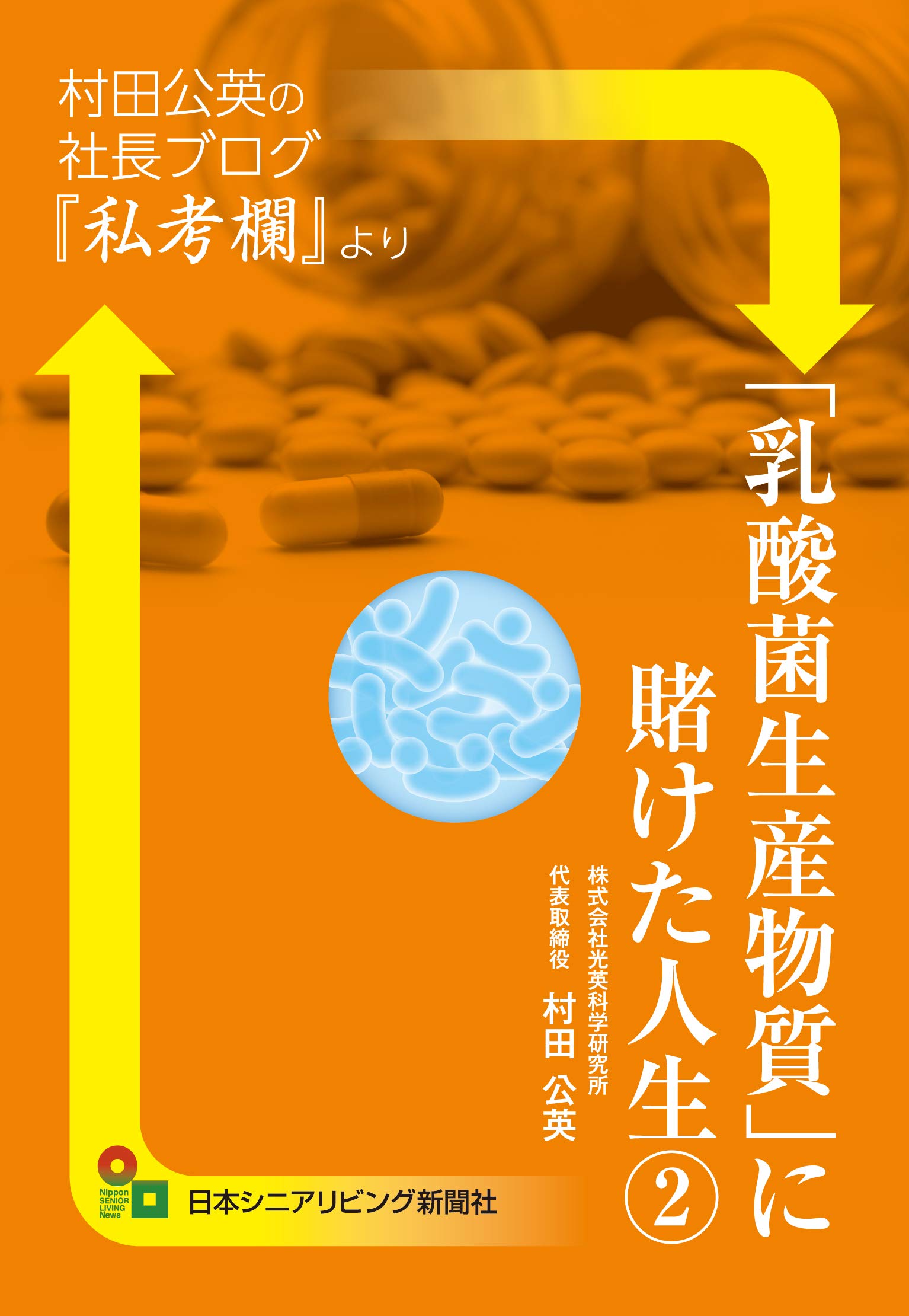2025.09.29
私的腸内細菌論
第179回 乳酸菌生産物質の製造の特徴⑧ 大型発酵タンクの働き
 秋冷の折、朝晩涼しくなり過ごしやすい陽気となってまいりました。
秋冷の折、朝晩涼しくなり過ごしやすい陽気となってまいりました。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、今回は当社の大型発酵タンクの働きを、私たちの大腸にある自前の発酵タンクと比較しながらお話をしてまいります。
どちらの発酵タンクも健康に有益な代謝産物をつくり出すことは同様ですが、発酵のメカニズムに相違点がございます。
まず、腸内細菌の栄養物(エサ)の摂取方法が異なります。
腸内発酵タンクの場合は、腸の内壁にびっしりと定着して連続培養を行っている腸内菌のチームが、小腸から供給された栄養物をそれぞれ自分たちのチームに適合したものを取得して、発酵を続けていると考えられます。

従って、腸内発酵チームには小腸から供給されてくる栄養物に対する選択肢がありますが、工場の発酵タンクの場合は栄養物である豆乳が大量(2,000kg)に用意されたタンクの中に16種35株のチームを添加して発酵をスタートさせますので、栄養物に対する選択肢がないために特別製の豆乳が必要であり、16種35株のチーム編成が最適な働きをするような製造技術が求められます。
そのため、多種多様な代謝産物をできるだけ大量に生産するチーム編成になっております。
これには、マザースターター(元菌類)からバルクスターター(編成菌群)に至るまで直径1.5mの円筒形状の培養タンク内にての編成チームの動向を設定することにより、常に定量の代謝物の生産が可能になりました。
試験管レベルの共棲培養システムをそのまま大型発酵タンクレベルにまで簡単に移行させることは不可能です。
長い年月をかけてそれを可能にして、多くの方々に乳酸菌生産物質をご愛用いただけることを、ぜひともご理解いただければ幸いでございます。
そして、大型発酵タンクの中で懸命に働いている「チームKOEI」に絶大なるエールをお送りください。
近年は健康食品市場だけでなく、一般的にも「健康には乳酸菌」という概念が定着しつつあります。
しかし、人の健康に役立つのは乳酸菌そのものだけではなく、その代謝物である「乳酸菌生産物質」がより重要です。
この本には、16種35株のビフィズス菌を含む乳酸菌の共棲培養技術のノウハウや、「乳酸菌生産物質」の商品化の知識など、私の視点から見た「乳酸菌生産物質」に関する情報が余すところなく盛り込まれております。
ぜひ第1巻に続き、第2巻もお手元で開いていただければ幸いです。
日本シニアリビング新聞社はこちらから
amazonはこちらから