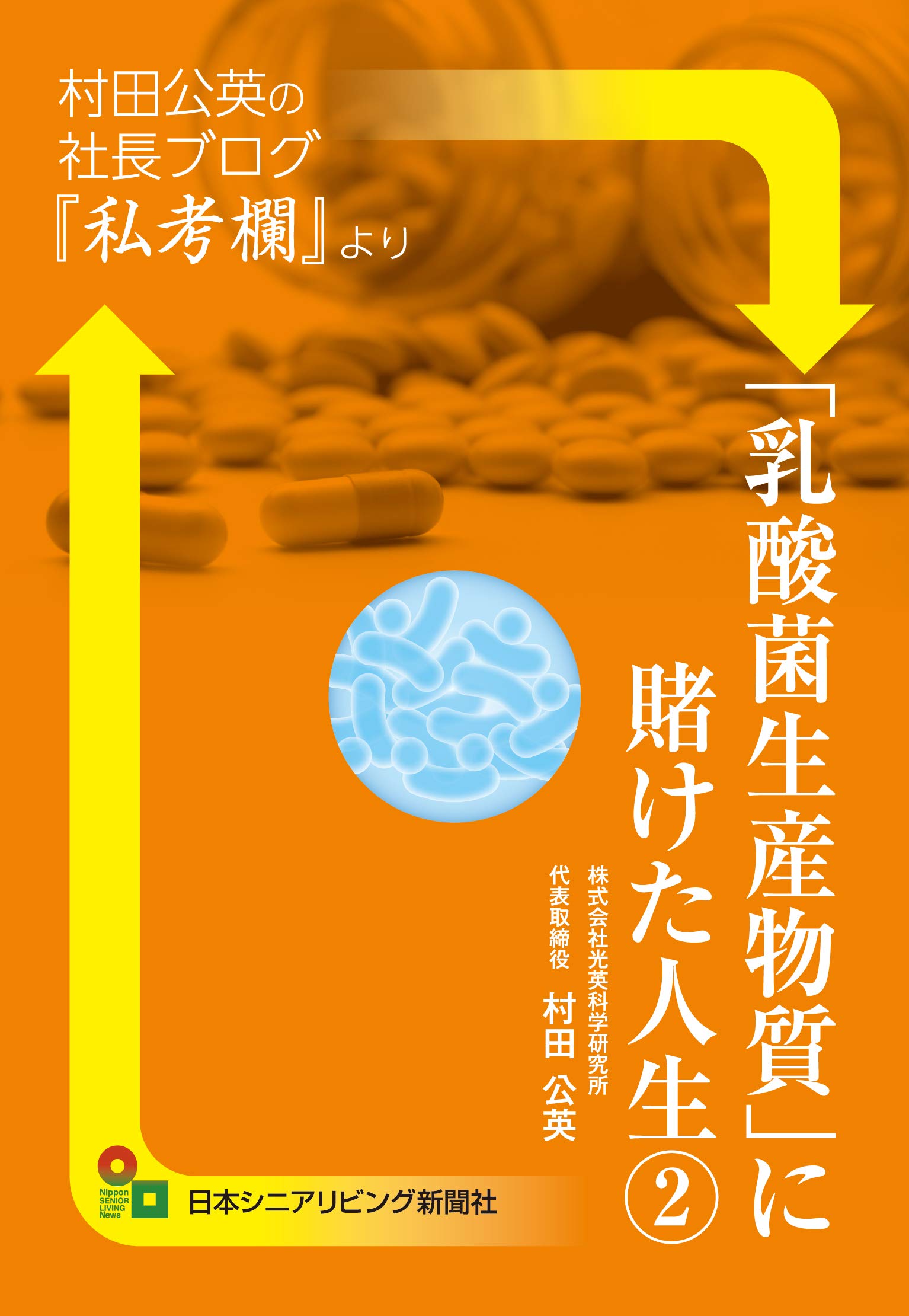2025.10.23
私的腸内細菌論
第180回 乳酸菌生産物質の製造の特徴⑨ 大腸発酵タンクのしくみ
 秋が深まり木々の紅葉が見ごろを迎えております。
秋が深まり木々の紅葉が見ごろを迎えております。
皆さまのお近くの紅葉はいかがでしょうか。
前回は工場の発酵タンクと私たちの体内にある大腸発酵タンクの中で腸内細菌群が発酵するための栄養物(エサ)をどのように摂取しているか、その違いをお話しました。
今回はそれぞれの栄養物(エサ)についての特徴をお話してまいります。
工場の発酵タンクの栄養物(エサ)としては、16種35株の善玉菌チームが充分に働いて、なるべく多くの代謝物をつくり出すように特別製の豆乳を設計して使用しています。
ところが腸内発酵タンクの場合は、腸内の善玉菌チームにとって簡単には栄養物が摂取できません。
その理由として、善玉菌専用の栄養物ではないことです。
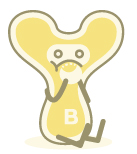 発酵の基本となる培地として小腸から送り込まれてくる栄養物等に加えて、大腸の粘膜から分泌される粘液成分から構成されていて複雑な性状となっていて、善玉菌にとって最適な成分だけではない状況となっているのです。
発酵の基本となる培地として小腸から送り込まれてくる栄養物等に加えて、大腸の粘膜から分泌される粘液成分から構成されていて複雑な性状となっていて、善玉菌にとって最適な成分だけではない状況となっているのです。
小腸から送り込まれる栄養成分にしても、そのヒトの食生活や体調によって変化して一定の成分が得られないのが実情です。
そして最大の難関は大腸内にはそのヒトに定着している善玉菌群の他に、悪玉菌と日和見菌群が存在していることです。
このように大腸内タンクの発酵に係る環境は善玉菌群にとって厳しく、デリケートな常態にありますが、一般的に善玉菌2・悪玉菌1・日和見菌7の割合を維持することが健康にとって大切だと言われております。
ここで注視しなければいけないのは、日和見菌の割合が7と圧倒的に多いことです。 日和見菌は培養が困難なためその性質が良く解っておりませんので未知の細菌として知られています。
善玉菌が優勢な時はそれを応援して有用な働きをしますが、悪玉菌が優勢になると一緒になって有害物質をつくります。
日和見菌を味方につけるには、善玉菌に活力をつけることですが、その方法については次回のお話にいたします。
お楽しみに。
近年は健康食品市場だけでなく、一般的にも「健康には乳酸菌」という概念が定着しつつあります。
しかし、人の健康に役立つのは乳酸菌そのものだけではなく、その代謝物である「乳酸菌生産物質」がより重要です。
この本には、16種35株のビフィズス菌を含む乳酸菌の共棲培養技術のノウハウや、「乳酸菌生産物質」の商品化の知識など、私の視点から見た「乳酸菌生産物質」に関する情報が余すところなく盛り込まれております。
ぜひ第1巻に続き、第2巻もお手元で開いていただければ幸いです。
日本シニアリビング新聞社はこちらから
amazonはこちらから